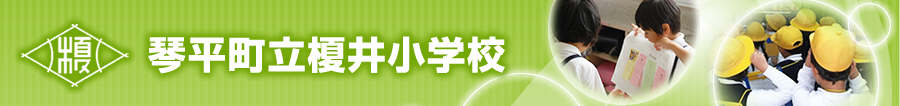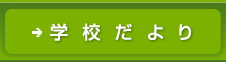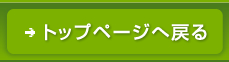- TOP
- まちづくり科研究のページ
榎井小学校の研究のページ
研究主題
新教科「まちづくり科」を通して、郷土を愛し、まちづくりに主体的に参画できる子どもを地域と一体となって育てる。
まちづくり科について
地方の時代、地方分権、地域主権などの言葉がもてはやされ、道州制などということも声高に主張され始め久しい。しかしながら、私たちの身の回りをながめてみれば、少子高齢化の影響が如実に見られ、人口の減少、若者の流出、人の手がはいらず荒れた山林や田畑など、高層ビルが立ち並び働く人が忙しく行き交う都会との格差は日増しに広がる一方のような気持ちにさせられるのも事実である。
学校教育は学習指導要領の趣旨から児童生徒に日本全国どこでも最低限の学力を保障し、その時代時代の要求、国民の願いに合わせ改訂されてきた。また、一人一人の学力の保障の過程において、児童生徒の生活環境、生育歴、自然環境などに合わせその指導法、教材の選定などを工夫することは当然である。こうした面で日本中それぞれの地域のよさが発揮されるはずである。
ところで今回の改訂の趣旨は次の点にある。
- 「生きる力」という理念の共有
- 基礎的・基本的な知識・技能の習得
- 思考力・判断力・表現力等の育成
- 確かな学力を確立するために必要な時間の確保
- 学習意欲の向上や学習習慣の確立
- 豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実
このことを踏まえつつ、前述の地方の疲弊を鑑みたときに、学校教育が果たすべき役割は小さくない。所謂、学力の高い生徒が都会に流出してしまう現象は高度成長期の過去から引き続いてはいるが、現在の少子化の波を受けて、その比率が年々高まっているような印象を与える。これは、都会に大学などの高等教育機関が集中していること、有利な就職先が数多くあること、自分の将来の夢がそこにあることなど様々な理由が考えられるが、自分たちの住んでいた地域や故郷に魅力を感じなくなっていることも原因の一つであると思われる。
今まで学習指導要領で示されている共通の教科学習等だけでは、子どもたちの中に自分たちの住む故郷に魅力を持ち、自分たちもその地域を形作っている一員だという意識を持たせることが十分ではなかったように思われる。
ところで、故郷を知り、故郷に愛着を持ち、故郷に住む人々と共感し、故郷を元気にするために参画できる児童生徒を育てることは、故郷の発展のため、延いては我が国の発展のために不可欠なことであると考える。そこで、琴平町の1中学校と3小学校では既存の教科・領域の時間数を削減し、郷土を愛し、まちづくりに主体的に参画できる子どもを地域と一体となって育てることを目指した新教科「まちづくり科」を創造した。
さて、琴平町は古くから金刀比羅宮を中心として栄えた。これといった娯楽が少ない江戸時代には、民衆にとってここ金刀比羅宮に参拝することが一生の宿願であり、自分たちの住む土地に縛りつけられた日常からの合法的な脱却であり、全国から参詣者が集まった。
例えば、金丸座で催されているこんぴら歌舞伎について考えても、天保6年に現存する金丸座が建設されたという記録が残っているが、町史によるとそれ以前からも琴平で歌舞伎が開催されていたようである。現在の歌舞伎が東京、京都、大阪、福岡などの大都会で定期的に催されていることから想像すると琴平の町はさながらこれらの都市と匹敵する賑わいがあったのではないだろうか。こうした金比羅宮が全国的に有名な神社となったのは元禄年間だと考えられている。町史からも江戸時代金比羅領内の人口は一番多い記録で5466人、平均すると2500人で推移したという記述が見られる。その当時の江戸の人口が100万、大阪は30万であり、現在の地図から琴平町の面積を計算すると1平方キロメートルとなり、人口密度は約2500人/キロメートルで単純に比較はできないが、現在の高松市や丸亀市よりも高い。このことから、琴平には多くの人が集まり、一大消費地であり、歓楽地を形成していたと思われる。したがって昔からそこへ消費財等を供給する産業、それを運搬する流通・交通が発達し、先程の歌舞伎をはじめとした文化も花開いていた。
ところで、現代に入り、琴平町は、各地の近代化、情報や交通の発達により、観光地としての魅力も相対的に減少し、観光客や観光地としての収益も頭打ちの状況にある。加えて周辺地区への人口の流出があり、少子化高齢化が県内でも急速に進んでいるのが現状である。これは琴平の魅力が薄れ、過去の憧れであった琴平の栄光が色あせてきているせいではないだろうか。しかしながら、この地域には人々の記憶から遠ざかっている史跡、隠れている文化、人々に知られていないすぐれた産業など先人が残した遺産が数多く埋もれている。こうしたうもれた奇貨を白日にし、『まちづくり』のために教材化し、地域にでかけそこに暮らす人々と交流し『まちづくり』に関する問題を明らかにすることで子どもたち自らが考え、進んで『まちづくり』へと参画しようとする意欲を高めたい。
また、この「まちづくり科」でねらっているのは、地域の人との交流、地域のコミュニティや行事への積極的参加である。これは子どもたちに早い時期から自分たちが社会の構成員であるという意識を持たせ、自分たちに地域社会かどうしてくれているかを知るだけではなく、自分たちが地域社会に何ができるかというシチズンシップをも培っていく。このことが一人一人に身につくように「まちづくり科」への態度として評価し、同時に、「まちづくり科」の学習の改善にも生かしていきたい。
このために、小・中学校9年間を通し、小学校第1学年から第4学年を基礎確立期、小学校第5学年から中学校第1学年を自己発見期、中学校第2学年と第3学年を自律期とし、それぞれの発達段階の課題を明確にして、まちづくり教育を推進する。基礎確立期には主に自分たちの住む地域やまちの様子を知り、まちに対する愛着を持たせること、自己発見期には学習をすすめることで、まちやまちにすむ人々に愛着を持たせること、自律期には、学習の完結として、まちづくりへの参加提案を行うことをねらいとし、それぞれの発達段階に応じたまちづくりへの参画態度も併せ養っていく。
こうして、実際にまちづくりに児童生徒自らがかかわり、そのことによりまちが変わり、自己効力感を実感することで自己を変容し、地域社会を担う一員として必要な資質を幅広く養いたいと考える。
本校の研究のあしあと
- 平成22年度研究のまとめ [PDF:6.25MB]